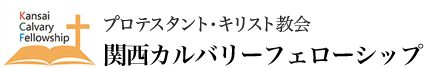心のオアシス
心のオアシス 2014年12月7日
ホラティオ・G・スパフォードが作詞した讃美歌の中に、世界的に歌われている聖歌476番When peace like a river「やすけさは川のごとく」があります。1800年代に活躍した裕福な弁護士であり、実業家でもありました。彼には奥さんと4人の娘さんがおりましたが、その娘さんたちが船に乗って大西洋を横断しているとき、この船が別の船と衝突事故を起こして沈没して、娘さん全員を失ってしまうとういう大変辛い経験をしました。彼は奥様からこの悲報を電報で受け取りました。悲しみに暮れている奥さんに会うために、大西洋を横断する船に乗りました。丁度、彼の娘さんたちが亡くなった辺りを船が差しかかったときに、ジッと渦巻いている波を見つめているのを、その船の船長が気付きました。その夜に、「やすけさは川ごとく」の歌詞を作詞したのです。
一番の歌詞は「安けさは川のごとく 心満たす時 悲しみは波のごとく わが胸満たす時 すべて 安し み神 共にませば」これは日本語訳でありますが、もう少し丁寧に訳すとこうなります。「川のような平和が伴うときもあります。また悲しみが海のうねりのように渦巻くときもあります。たとえ自分の運命がどのように見えたとしても、神様、あなたは私に「安らいでいなさい」と教え諭してくださいます。私の心は安らかです」
時々、私たちは、自分の人生に起こる様々な重荷に潰されそうになります。それは、仕事のトラブルであったり、人間関係のストレスであったり、病気であるかもしれません。それらの問題は、とても大きく私たちの生きる気力を失わせる壁になっていることさえあります。しかし、私たちの運命が、どのように見えたとしても、神様のご計画は、私たちが考えているようなちっぽけなものではないことをスパフォードの詞を通して学び勇気づけられます。歌詞の中にある「すべて安し」とは、自分が基準であるならば、そうは思えないでしょう。でも、偉大なる神さまの手の中に自分は生き、動き、存在していることを信じることができるならば、そう思えてくるのです。キリストの平和がありますように!
心のオアシス 2014年11月30日
「アルコール依存性の詩」後藤光代著からの抜粋です。
私は、お酒を憎んできました。お酒漬けの夫を憎んできました。お酒が憎いのか、夫が憎いのか、そのどちらも憎いのか自分でも分からないくらい、すさまじいエネルギーを流し続けてきました。「そのすさまじいエネルギーがあなたですよ。そのことに気付きなさい。」夫のアルコール依存症が、自分に自分が伝えるメッセージであったなどとは、おそらく、心を見るという学びに繋がらなければ、絶対に思いもしないことだったと、私は思っています。・・・今の私は、幸せなんです。自分のすさまじいエネルギーを周りにぶちまけてきた結果が、これまで自分自身が味わってきた苦しみ、悩み、憂いだったことを、私はほんの少し感じているからです。夫ではなかったし、子供でもなかったのです。やはり、彼や彼女たちは、私にとってはかけがえのない家族でした。アルコール依存症の夫が、酒を絶ってくれたなら、私は幸せになれる、万事うまくいく、そう思い込んで、そのために東奔西走してきた自分でした。精一杯生きてきたと自画自賛してきたけれど、結局、私は、一番大切なことを見落として頑張ってきたのです。自分が頑張ることが、さらに新たな苦しみを生んでいくとは、私には、なかなか分かりませんでした。今は、「そんな私もみんな受け入れたよ」って、自分に言ってやれる余裕が出てきています。夫の心の叫び、そして、自分の心の叫びを真正面から聞く優しさに欠けてきた自分でした。ただ、酒が好きなだけ、そう夫に言わせるその心の底をくみ取る優しさに欠けていたのでした。自分がまず幸せだったと気付くこと、何がなくても、もう自分はすでに幸せだったことに気付くこと、これでした。幸せになろうではなく、幸せにしてくださいではなく、私は幸せな存在でしたと、ほんの少しでも心で感じられて、そして、私の人生の幕引きができれば最高だと思っています。人って優しいなあ、私って優しいなあ、チラリとでも本当にそのように思える日が来るのを楽しみに、日々を過ごしてまいります。
「いつも喜べ。絶えず祈れ。すべての事に感謝せよ。」(Ⅰテサロニケ5章)
心のオアシス 2014年11月23日
世界的に有名な曲「驚くばかりの恵みなりき」Amazing Graceの詞を書いたジョン・ニュートンは、神様の恵みによって、その人生が大きく変えられた人物の一人です。彼は奴隷船の船長で、人を売買し奴隷を人間扱いしない冷酷な血も涙もないような人間でした。ある時、大嵐の中で、船が木の葉のように揺れて、命を落とすかもしれないという状況の中で、彼は一冊の信仰書を通して、神様の恵みに触れました。それから彼はイギリスに帰ってから、奴隷船の船長を辞め神様に仕える者となりました。そして牧師になって、神様がどれだけ自分に恵みを注いでくださったかを宣べ伝えるようになったのです。そのことが、彼の歌の中にも表れています。「驚くばかりの恵みなりき、この身の汚れを知れるわれに」
あまりにも有名な曲ではありますが、残念ながら日本語訳の歌の歌詞には、作詞者の思いの半分も伝えられていないのが現状です。英語の直訳は「アメイジング グレイス『驚くばかりの恵み』とは、何と美しい響きでしょうか。私のような者までも救ってくださり、道を踏み外し、さまよっていた私を神は救い上げてくださり、今まで見えなかった神の恵みを、今は見出すことができるのです」
私は自分が何のために存在し、生きているのかわからないまま生きていました。自分という存在が、この世から消えたとしても、それで何の影響があるのだろうか? とも考えていました。中学2年生の時、教会の門をくぐり、神様に生かされていることを知り、神様の恵みなしに生きることはできないということを悟ったとき、私の中に変化が起こりました。「見るもの全てが美しい」という感覚で、同じものが生き生きと見え始めたのを覚えています。劣等性でしたが、神様の恵みは、何ができるとか、成績が良いからではなく、どんな愚かさも包み込む懐の広さがあることを知り、私の人生は全く変えられたのです。私の「今」は、神さまの恵み以外何もありません。それは弱さの中にある強さだと自負しています。神さまの恵みは、どんな人をも変える力を持っているのです。
心のオアシス 2014年11月16日
C.S.ルイスは著書 「偉大なる奇跡」の中で、次のように述べています。「ある建物の中に、どれだけかの人がいるとします。半分の人たちは、そこをホテルだと思っており、もう半分の人たちは刑務所だと思っています。そこをホテルだと思っている人は、我慢できないひどい所だと言い、刑務所だと思っている人は、思いのほか快適な場所だと言います。」
人生の捉え方は、その人が人生をどういうものだと思っているかによって、ずいぶん違ってきます。ルイスは、ホテルと刑務所という対比を使って、そのことをうまく説明しました。彼は言いました。「この世は自分が幸せになるためにあると考えるなら、そこは我慢できないひどい場所かもしれません。一方、この世は訓練と矯正の場だと考えるなら、それほど悪くはない場所だと思えるでしょう。」
私たちは、この世が訓練と矯正の場だとは考えたくもないでしょう。そればかりか、人生は苦労のない幸せなものであるべきだと考えます。しかし、そのような思いとは裏腹に、幸せだとは思えない出来事が次から次へと出てきます。自分の基準が、何の問題もない「幸せな人生」であるならば、それらの出来事にストレスを覚え、耐えることができなくなってしまうこともあります。聖書を調べてみると、どこにもこの世は住み心地の良い場所とは書かれていません。そればかりか、イエス・キリストは「あなたがたは、世にあっては患難があります。」(ヨハネ16:33)と言いました。その他、聖書には様々な箇所に、この世は、良い時も悪い時もあって、霊的に成長するための場所であることを記しています。
霊的に成長するとは、どういうことでしょうか? それは、この世が混沌とした世界であっても、その中で天国に住んでいるかのような生き方をすることができるということです。辛いできごとや悲しいできごとの向こう側に、希望があることを信仰の目で見て生きるのです。
神は主権者です。ご自分の計画にしたがって、すべてを治め、指揮しておられます。ですから私たちは、人生の浮き沈みに際しても、心に平安を保つことができるのです。この世はそんなに悪くはないですよ。
心のオアシス 2014年11月9日
7月上旬頃の事です。普段は仕事から帰り、一緒にご飯を食べ、一緒にお風呂に入り、家の用事をして、それから子ども達と触れ合う時間を持っていました。しかし疲れている時は、自分の時間を持つために子ども達に録画したアニメ番組を見せ、子ども達もテレビを見る事が当たり前になっていました。これはよくない!と日頃から感じていました。その日、一人で事務所にいた時に、「イエス様、このままで良いのでしょうか?」と祈りました。わたしは家族の祝福を心から願っています。しかしイエス様の助けなしに子育てというものはできるものではないと思っています。その為に、まず親として、子の模範でなければならない!と考えたのです。いつもテレビや自分の好きな事に時間に費やす姿を見せるのではなく、イエス様を第一にする姿勢で、聖書を読み、一緒にお祈りをしていこうと思いました。今までケーブルテレビで好きな番組を録画して、好き放題に見れる環境がありましたが、すぐにケーブルテレビを解約しました。それから私もしばらくテレビは見ないで、聖書を読む時間に費やそうと決断しました。朝早く起きて、家の用事をする前にまず聖書を読む、祈る。そして仕事を終えて、自分の部屋に入ったら、今まで自分の好きなことをしていましたが、聖書を読むことを優先する。夜読むことは、今まで自分にできていなかったことです。そしてさらに土曜日や日曜日の午後の昼間も時間を作り、聖書を読む工夫をしました。すると心が平安になるのです。時に怒る時もありますが、仕事も家事も子育ても、余裕をもって何事にも取り組めるようになりました。これは神様が与えてくださった祝福であると信じています。聖書を読む時間が増えていくと、聖書の世界が自分の中で広がってきて、恵みが豊かになる感覚が増えてきました。子ども達とも毎晩一緒にお祈りするようになり、長男は新約聖書を通読することができました。(文責:道本賢司)
「神の国とその義とを、まず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。」(マタイ6章33節)
心のオアシス 2014年11月2日
大和カルバリーチャペルに、極度のウツと対人恐怖で、人と接することができないので、礼拝にも出ることができなくなってしまった一人の青年がいました。調子が良いときに、勇気をふりしぼり、いくつかある礼拝の中でも、一番人数の少ない火曜礼拝という昼間に行なっている集会に来られるようになりました。当時、副牧師であった私は、この方と関わっていましたが、このような嬉しいメールをくださいました。
「『人生で最もつらかった時期はいつですか。その時経験した神の恵みは何ですか?』と、リビングライフに質問が書いてあって、真っ先に、クリスチャンなのに、神様のことがわからなくなって、苦しくさまよっていたあの時のことが思い浮かびました。でも、その時経験した神の恵みは、火曜礼拝と先生との交わりだったなぁって、今でも思い出します。お正月の終わり頃、小崎先生と倉知先生が、外が暗くなるまで時間を費やして、お話ししてくれたこと。本当に、信仰とは全く関係ない、日常の話でした(笑)。でも、私はあの時、教会の誰とも話すこともせず、家でも会話せず、仕事もしてなかったから、本当に誰とも話さずに生活していました。頭の中だけを、苦しい思いが回っていました。『 あー、こんな私のために貴重な時間をさいてくださる人がいるんだ。』薄暗くなった帰り道を、感動しながら帰ったのを今でも覚えています。 あの時から、神様に捨てられてしまったんだと思っていた私の心に、少しずつ、少しずつ、神様の御言葉が入ってくるようになったのです。それから少しずつ、お話しすることも、笑うことも、眠ることもできるようになっていきました。神様は、たった一人の私のこと、諦めないでいてくださったのです。昨日は、前から2列目で、第二、第三礼拝に出て、おひるごはんもシャローム館で食べることができました!」 (中略)
先日礼拝前に、私たちの教会で洗礼を受けて実家のある九州へ転居された方から「今日は、なんとあの父が受洗します!」という驚きメールが入りました。お父様は大阪に来られた時に、一度だけ礼拝に出られましたが、祈りを通して聖霊さまが届いて下さっていたのです。栄光在主!
心のオアシス 2014年10月26日
フィリピン諸島には、大小さまざまな島があり、その中には無人島もあるそうです。その中にカオハガン島という東京ドーム1つ分ぐらいの面積の島があるのですが、何とその島のオーナーは日本人で、78歳の崎山さんという方だそうです。今から26年前に1千万円で購入したとのこと。しかし購入した当時から島民がすでに住んでいました。島のオーナーですから、そこから島民を追い出すこともできたのですが、それをしませんでした。そればかりか、ガンの手術費用のない男性には、自腹で手術代を出してあげ、生活力のない人たちに自給できるよう仕事をつくり、教育を施し、島のオーナーであるにもかかわらず、島民のために走り回る日々を送っておられるのです。
「どうして、あなたは島のオーナーなのに、そんな親切をするのですか?」という質問に、崎山さんはこう答えていました。「ある本に、このようなことが書かれていました。『土地は元々、人の所有ではなく神のものであって、我々は借りているにしかすぎない。借りている間に、それを良くして返すもの』と・・・だから、この島も自分の物ではなく神からの借り物。自分が借りている間は、この島を良くして返そうと思ったから」というのです。
私たちの体も、家も、健康も、仕事も、経済も、すべて神さまからの借り物です。この地上における激しいレースを乗り越えていくために神さまが貸してくださっているものです。死ぬときには、全て地上に置いていかなければならないのです。「自分が働いて、努力して、切り開いて、儲けて生きているのだから、自分の人生、自分の好きなように生きてもいいのではないか?」と考える人は多いです。では、自分の好き勝手に生きて、どうしても乗り越えることができない壁にぶつかったら、その時は神に求めるのでしょうか? 勝手すぎると思います。神さまから貸し出されているものを、神さまのために用いて生きることが、この地上での本来の用い方なのです。そのような生き方からは、限界を感じることはありません。なぜなら神さまが保証してくださっているからです。
心のオアシス 2014年10月19日
一般の成功法則は「自己実現するためにはどうしたらよいか」と語るものが多くあります。それゆえに自己啓発という言葉があります。これには何も問題がないようですし、魅力も感じてこの手の法則に飛びつく人たちも多くいます。しかし、聖書が教えている成功する秘訣は「神実現」にあります。「自己実現」と「神実現」には大きな違いがあります。「自己実現」は「今の私は、まだ自分が望む地位や存在価値に到達していないから、そこにたどり着くために頑張ろう」という概念が潜んでいます。時には明確にそれを主張しているものもあります。つまり、その人のセルフイメージは、まずは根本的に低いところにあって、そこから這い上がるという図式であります。這い上がるために、どうするのか・・・ということを教えるのです。でも、這い上がれない人や、這い上がる気力のない人は、どんどん振り落とされてしまいますし、諦めてしまうのです。そしてまた他の方法を見つけては、それで這い上がろうとしては、失敗の繰り返しであります。
しかし聖書が教えている人間の地位は、神が創造したものの中で、最初から最高の地位にあるということです。これ以上ないほどの成功を遂げた姿こそが、私たち本来の姿なのです。イザヤ書43章に「わたしの目には、あなたは高価で尊い。わたしはあなたを愛している」ということ・・・私たちは、もともと最高の地位にいるものとして創造された・・・というところからのスタートなのです。神さまがわたしを愛していることを知ることが重要なのです。私たちの努力は必要ありません。「努力する」のではなく、「知ること」で道が開けてきます。
聖書が語るセルフイメージによれば、私たちはまだ得ぬ地位を獲得せよというのではなく、本来のステイタス(地位)を回復するだけでよいのです。王様に子どもが生まれたら、その子は自己努力ではなく、ただ「王様の子どもだから」という血筋によって王位を継承することができるのです。 (「聖書に隠された成功法則」より抜粋)
全て人は「神の子ども」です。そこに気づくことができますように。
心のオアシス 2014年10月12日
ある人が、古本屋で一枚の古い地図を安く買いました。それを買った価格より少し高い値段で売ろうとしましたが、結局その地図の買い手は見つかりませんでした。彼はその地図を売ることも捨てることもできず、本棚の隅に押し込みました。ある日、歴史学の教授である友人が家に来ました。いろいろと話をするうち、ふと地図のことを思い出して、言いました。「随分前に古本屋で買った地図があるんだが、一度見てくれないか? もちろん、そんなに大したものではないだろうけどね・・・」その友人は難しい頼みでもなかったので快く引き受けました。そして本棚から持ってきた地図を見てすぐ、友人は驚きの声を上げました。その地図は、ルイ14世の当時に王の命令でパリの市街地を描かせた地図だったのです。地図は1650年代に描かれたもので、当時のお金で計算すると100万ドル(約1億円)以上の価値のある宝物でした。彼は溜息をつきながら友人に言いました。「私がもう少し早く知っていたら、今よりいい暮らしをしていただろうに。しかし、誰のせいでもないよ。私が知らなかったせいだから・・・」
ニック・ブイチチは、四肢欠損症で生まれたオーストラリア人です。彼は物心ついたころから自分の人生の意味も価値も見いだせませんでした。神に「どうして僕を手足のない形に作ったのか?」と問い続けていました。ある日、神さまから「あなたはわたしを信じるか?」この質問に「はい、信じます」と答えたときに全てを受け入れられるようになったと彼は告白しています。そして「たとえ手足があったとしても平安は得られないことに気付きました。この世には、僕に満足のいく答えを与えてくれるものは何もありませんでした。自分は何者で、何の価値があり、どこへ行くのか・・・イエス・キリスト以外に答えを見つけることはできなかったのです。」
絶望しか残っていない人物に、生きる意味と希望を与えることができる宝が、あなたのすぐ目の前にもあることに気づかないのは、大損です!
心のオアシス 2014年10月5日
韓国での5年間の学びを振り返ると、神様が働いていて下さったんだな、と思える出来事がいくつもありました。韓国へ最初に行った時は韓国語が話せなかったので、良い友達が与えられるように祈りました。すると、最初のルームメイトである台湾人の留学生と仲良くなることができました。毎朝一緒にデボーションをしたり、夜には祈祷会をしたりして、信仰の友を得ることができました。
あるとき、その友人が祈りのリクエストとして学費が不足していることをあげました。今学期の学費が払えていないため、もう大学を辞めなければいけないと泣きながら祈っていました。その時私が父を少しでも助けようとアルバイトを掛け持ちしながら貯めていた貯金があったのですが、友人が必要としていた金額と同じだったのでこのように祈りました。「神様、このアルバイトもお金も神様が下さったものです。神様が喜ばれるように使うことができますように。私の学費や父の助けは神様が下さると信じます!」そして貯めていた全額を友人に渡しました。
その次の週、私がインターンをしていたヨイド純福音教会から一本の電話が掛かってきました。「外国人の神学生を助けたいと、4年間の学費を出してくださるという長老様がいるんだけど、恵さんを推薦しましたよ。」こうやって神様は不思議なようにして4年間の学費を与えてくださいました。また、それは父が大阪へ開拓をしに出た年でもありました。後に父から、「子どもの学費をこの先どうしようかという不安はあったけど、神様を信じて関西に出てきたんだよ。恵から奨学金の話を聞いた時は本当に驚いたし、神様に感謝したよ。」といわれました。神様は人々の心からの祈りに、必ず最善の形で答えて下さる素晴らしい神様だな、と実感した出来事でした。(文責:小崎恵)
右も左もわからずに留学した娘が、親からの経済援助はほとんど無しで学校を卒業してしまいました。娘に能力があったからでしょうか? いいえ、「この奥義は、あなたがたのうちにいますキリストです」(聖書)