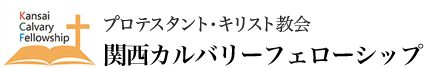心のオアシス
心のオアシス 2019年1月20日
今日は第三回目「完璧主義による傷の対処法」です。
恵みを頭で“知っている”ことと、恵みの人生を“生きる”こととは違います。私たちは、恵みによって生きなければなりません。恵みの法則を子どもの養育にも適用するなら、恵みの祝福があなたの家庭と子どもに豊かに臨むことでしょう。成績が落ちたときや失敗したとき、財布をなくしたとき、子どもが親の気に入らない行動をしたとき、子どもが罪悪感にさいなまれているとき、神さまは、ありのままの姿で愛しておられ、あなたを見ているだけで喜ばれていることを伝えてあげましょう。
ある夫のストーリーです。その人は、子どもの頃から父親にほめられたことがありませんでした。自分なりに勉強もがんばり、努力もしましたが、父親はいつも批判と指摘と叱責を繰り返しました。また、お金も惜しみ、条件なしにくれる小遣いやプレゼントもありませんでした。そのようにして成長した夫は、自分の父親をとても嫌っていました。ところがおかしなことに、結婚後、自分もその父親と同じように子どもや妻に対して行動していることに気がつきました。いつも感謝も満足もありません。このような場合、どうしたらいいでしょうか? まず、夫の心のうちを理解してあげましょう。夫は、からだは成長していても、今でも褒められ、認められることに飢え渇いている子どもと同じ状態です。自分自身のことを、受け入れられないので、自分を責めているのです。自分がありのままの姿で受け入れられ、愛されている存在だということを信じることができず、その心の状態を妻と子どもに映し出しているのです。そのような夫は、神さまの恵みを理解することができません。まず、夫が神さまの恵みを深く知ることができるように祈りましょう。そして、夫の行動に対して過剰反応したり批判したり指摘するのもやめましょう。神さまがありのままの姿を受け入れ愛しておられることを伝えましょう。ただ神さまの恵みだけが、完璧主義の考え方を変えることができ、傷を癒すことができるのです。(イ・キボク師文章抜粋)
私のライフメッセージも、「それでも神はあなたを愛している」です。
心のオアシス 2019年1月13日
完璧主義の陥る危険性について、先週からお分ちしています。今日は、第二回目「親の完璧主義が子どもに与える影響」です。
完璧主義の親は、子どもに「失敗してはダメだ」「もっとがんばりなさい」「最善を尽くさなければならない」「まだ少し足りない」という言葉で限りなく要求します。すでに達成した成果については、励ましたり認めたりしません。表現したとしても微々たるもので、強調して伝えることは「さらに努力しなさい」というメッセージです。そのため、完璧主義の親は、子どもがどんなに頑張っても、称賛せず、満足感を伝えません。過剰な期待を持ち、さらに努力して最高の成果を出すよう要求し続けることが、完璧主義の特徴です。
そのような完璧主義の親のもとで育った子どもは、満足され、認められ、褒められ、励まされることに飢え乾いています。初めは自分でも最善を尽くして親の期待に応えようとしますが、だんだん手に負えなくなります。心の中で「私はダメだ」「私はいつもこうなんだ」「親を喜ばせることは不可能だ」と考えるようになり、結局は自暴自棄になってしまいます。そして、自分自身に怒りと挫折感を感じたりもします。そして、限りなく完璧を求める親に憤りを感じるようになります。完璧主義の親が子どもに与えるメッセージは、子どもに測り知れないストレスと傷を与えるということを知ってください。限りない期待と要求ではなく、子どもの小さな達成に対しても、惜しみなく称賛と励ましを表現する親になりましょう。(トーチ・トリニティ神学大学教授・イ・キボク)
親は子どもを褒めているような気になっているかもしれませんが、子どもからすると9の要求に対して1しか称賛されていないと感じているようです。もし神さまが私たちの足りない部分を毎回指摘されたら、やってられなくなりますよね。愛し育てる“愛育”によって本心から自発的に動けるようになるのです。存在してくれているだけで感謝!と考えれば、要求することも少なくなると思います。親のエゴ(親実現)は、子どもに傷と反発を生み出します。やはり神実現に尽きますね!
心のオアシス 2019年1月6日
トーチ・トリニティ神学大学教授のイ・キボク先生が、私たちが陥るある危険について的確に文章に書かれていましたので、何回かに分けて抜粋してご紹介します。私たちの生き方の指針になればと願います。
恵みとは何でしょうか。恵みを理解することは簡単ではありません。なぜなら、この世はすべて“恵みでないもの”によって動いているからです。この世は、成功し、満足を得るために、努力本位、成果本位、功績本位、資格本位によって動いています。しかし、恵みの法則は全く違います。恵みとは、「それを受ける者の資格とは全く関係なく」与えられる愛とあわれみと祝福を意味するものです。ただ恵みを施される方の一方的な品性のゆえに与えられるものなのです。「あなたがたは、恵みのゆえに、信仰によって救われたのです。それは、自分自身から出たことはなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。だれも誇ることのないためです」(エペソ2:8~9)では、恵みを受けることができる信仰とは何でしょうか。それは行いではありません。信仰とは、神さまが与えてくださる恵みを、ただ謙虚に受け取る姿勢でもあるとも言えます。その恵みにお返しをする方法はありません。恵みを受けた人は、ただ感激と感謝をささげるだけです。その結果、恵みを受けた者として、主の御心に従って生きるようになるのです。
私たちの家庭の中には、知らず知らず完璧主義が働いています。完璧主義は、「何の失敗もなく最高レベルで、すべてのことを完璧にすること」という非現実的な期待のようなものです。それは、私たち人間の弱さと限界を認めないことに起因しています。神さまは、弱く失敗する私たちを愛してくださっているという恵みを忘れることです。私たちは人間なので、不完全で失敗するしかありませんが、神さまの恵みと助けに拠り頼んで生きていくとき、素晴らしい人生を歩むことができるということを忘れてはなりません。恵みの反対が、完璧主義なのです。
次週は、親の完璧主義が子どもに与えている影響をお分ちします。
「キリスト・イエスにある恵みによって、強くなりなさい。」(Ⅱテモテ2)
心のオアシス 2019年1月元日
昔、イギリスのある変わり者のバイオリニストが演奏会を開きました。友人をはじめ、観客がたくさん集まり、演奏が終わると、熱烈な拍手が起こりました。その瞬間、彼は演奏していたバイオリンを急に床に投げ捨てて足で壊し始めました。彼が再びもう一つのバイオリンを持ってくると、司会者が言いました。「今、彼が演奏したバイオリンは、実は20ポンドの安物でした。今から最高のバイオリンで本格的な演奏を始めていただきましょう。」今度の演奏もまた大きな感動を呼び起こしました。しかし、正直言って、観客はその2つの演奏に大きな違いを感じることができませんでした。この日、バイオリニストの奇行を通して観客に伝わったメッセージは、「偉大な音楽家が偉大な音楽を作り出すのであって、偉大な楽器が偉大な音楽を作り出すのではない」ということだったのかもしれません。
イエスは人を通して世を変えようとされました。イエスの公生涯は、イエスが用いる人を選ぶことから始まりました。しかし、その選択基準は、世とは全く異なっていました。イエスは、ガリラヤの漁師やさげすまされていた取税人のように、世の中で何一つ自分を誇ることができない人々を神の国の柱のような存在として用いられました。イエス・キリストは今も弟子たちを呼んでおられます。私たちに弱さや咎があっても、主の御手に捕らえられるなら、神の栄光が現れ、世が変わり始めるのです。(わかりやすく解いたマルコの福音書の話(上)/イ・ドンウォン著)
聖書的に言うならば、私たちは土の器のような存在です。離せば落ちて、落ちれば割れてしまう器であっても、誰の手の中にあるかということによって、その価値は変わってくるのです。イスラエルの民が40年間砂漠をさまよう中で生き延びることができたように、2019年は、是非、神の手の中にある安心を手にしていただきたいと願っています。たとえあなたが、神を知らなくとも、神はあなたを知っていて、一方的に大切に思っていてくださっているのです。良き一年となりますように。
心のオアシス 2018年12月30日
今年も残り少なくなりました。この時期になるといつも一年を振り返って感謝を神さまに捧げるようにしています。そしてその感謝は、関西で開拓を始めた8年前にさかのぼります。当初は、礼拝できる集会所の一室があり、3人の方が来てくださることに感謝していました。それから毎年のようにして不思議なことが起こりました。子どもの数が少しずつ増えてきた時に、道本賢司先生が、「是非とも開拓をお手伝いさせてください!」と自ら私たちの教会に飛び込んでこられました。教会のホームページを充実させる必要が出てきた時に、その道の達人が教会に加えられました。集会所から追い出される事態になった時、藤長先生が快く東大阪福音教会の石切チャペルを貸してくださいました。そして遠い未来の夢であった聖歌隊がこんなに早く結成されようとは想像していませんでした。娘が牧会を手伝ってくれるようになってヤングチャペル(中学生礼拝)会や青年会が出来上がり、礼拝の音楽の奉仕などを中高生が仕切るようになるとは、夢のまた夢でした。そして礼拝前に強制的?にコーヒーをサービスする教会になるなんて、これも想定外でした。関西聖書学院から毎年神学生が派遣されて助けてもらえるようになりました。ダンディーな男性たちの有志がカルテットを、愛らしい子たち?のフラダンスチームも結成されました。昨年には役員の方々が選出され、堺にレストラン教会まで与えられました。表ばかりの奉仕だけではなく、裏で祈ってくださり、静かに礼拝に出席される方、チラシを配ってくださる方、献金をしてくださる方、誰に言われるわけでもなく掃除をしたり、ゴミを持って帰ってくださる方々、その他様々な方々の働きによって、教会は支えられています。開拓当初はすべて私一人でしていましたが、神さまが必要な時に、必要な存在を周りに置いていてくださっていることに不思議を感じ、感謝が尽きません。
私たちの歩みは、誰かによって支えられていて、その背後に神さまの手の働きがあるということを知る必要があると思います。今年も奇跡の連続でした。そして新しい年も、それは継続するでしょう。良いお年を!
心のオアシス 2018年12月16日
1897年、バージニアという8歳の少女から、「サンタクロースって本当にいるの?」いう質問の手紙を受け取った「ニューヨーク・サン新聞」の記者は、それに対して新聞社の顔ともいうべき社説に、その答えを書きました。それが、世界中で大反響を呼び、世界で最も有名な社説のひとつとなり、本にもなりました。やりとりの内容はこうです。
ニューヨーク・サン紙さま
わたしは、8才の女の子です。私の友だちは「サンタクロースなんていない」と言います。パパに聞いたら「もしサン新聞の記者さんに聞いて、サンタクロースが本当にいると言われたら、そのとおりだと思うよ」と言いました。だから本当のことを教えてください。サンタクロースは、本当にいるのですか? バージニア・オハロン 西495番街115番
バージニアへ
君の友だちは、まちがっていますよ。その子たちはきっと、疑い病にかかっているのだと思います。人は自分に見えるものだけしか信じないし、自分の小さな心で理解できないことは何でも否定してしまいます。
もし、サンタクロースがいないとするならば、あなたは手に触れられるもの、目に見えるもの以外で、幸せを感じたことはないですか? 目に見えなくても、手に触れられなくても、幸せって感じられるはずです。ひょっとすると、それがサンタクロースなのかもしれませんね。
1897年12月24日 ニューヨーク・サン紙
“信仰”とは、現実には“無い”と思われるものを、“在る”と信じ、それがあたかもあるかのようにして生きることです。神様は目で見えなくても、手で触れることができなくても、たとえその存在を否定したとしても、どのような人の中にも、確実に共に生きて働いておられます。そして、クリスマスは、その存在が明らかにされた日です。
「きょうダビデの町に、あなたがたのために救主がお生れになった。このかたこそ主なるキリストである。」(ルカ2章11節)
心のオアシス 2018年12月9日
ミルトン・エリクソンという心理学者と、あるおばあさんの実話です
ある時、エリクソン博士の旅行先に、お金持ちのおばあさんが訪ねてきて言いました。「私はお金に不自由は全くなく、大邸宅に住んでいます。イタリアから取り寄せた見事な家具に囲まれて、コックが毎日、素晴らしい料理を作ってくれます。園芸は好きですが、身の回りのことは全部メイドがやってくれます。けれども私ほど不幸な者はいません。寂しくて寂しくてたまりません」博士はその話を黙って聞いていました。「わかりました。あなたは教会に行きますか?」「時々行きます」「では、あなたが行っている教会の人たちのリストを作って、誕生日を書き入れてもらいなさい。そしてあなたは、育てた花に綺麗なカードを添えて、誕生日が来た人の玄関前に、置いておきなさい。ただし、あなたからということは知られてはいけませんよ。もしそれで幸せになれなかったら、また私のところにいらっしゃい」と博士は言いました。その老婦人は、さっそく試しました。朝三時に起きてこっそり鉢を届けるようになりました。そのことが町では「天使が来た!」と評判になりました。その人はエリクソン博士に電話をかけて、「宿題は成功しています」と報告しました。博士は「あなたは、まだ不幸ですか?」と聞くと、老婦人は「えっ、私が不幸だなんて・・・」と答えます。「でも、あなたは半年前に私のところに来て、『私は、お金もあるし立派な家もあるけれど、寂しい』と、私に話したではありませんか?」とエリクソン博士が言いました。
3ヶ月が経ったクリスマスの朝、その老婦人からエリクソン博士にまた電話がかかってきました。「先生、今日のクリスマスほど不思議なクリスマスはありませんでした。門のそばに置いた大きなクリスマスツリーの下に、私の必要なクリスマスプレゼントがたくさん置かれていました。誰から贈られたのかわかりません・・・」エリクソン博士は言いました。「是非、受け取ってください。あなたが庭に種を蒔くと、その種は花になってあなたのところに返ってきます。あなたは小さい種をいっぱい蒔いたから、立派な花になってクリスマスに返ってきてくれたのですよ」
心のオアシス 2018年12月2日
どん底からサンタクロースになった男の実話です。
場所はアメリカ。ラリーという青年は、貧しい家で育ちで、「お金があれば幸せになれる!」と信じ会社を設立。しかしわずか数カ月で倒産し、8日間飲まず食わず街を徘徊していた。気がつくとレストランで食事をしていた。彼の前には19ドルちょっとの数字がかかれた伝票が置かれた。無銭飲食で捕まる覚悟を決めた彼に、レストランの店主が意外な行動をとった。「あの、これ落としましたよ」と言って、20ドル札を差し出したのです。「店主の勘違いだ」と思いながらも、それを払って難を逃れた。「ラッキー!」その時はただそう思った。そして4年後、再び会社を設立するが、また倒産する。借金は膨大に膨らみ、銀行強盗をしようと、ピストルを出そうしたまさにその時、4年前の記憶がよみがえった。「あの20ドル札は本当に落し物だったのか?!」確かめるために、レストランに行くと、店主は意外な事を言った、「クリスマスは誰もが幸せになれる日なんだよ」銀行強盗をしなかったのも、その時無銭飲食でつかまらなかったのも、あの時の20ドル札のおかげだった。ラリーは今度こそ改心し、コツコツと働く道を選んだ。やがて結婚し子供にも恵まれた。
そんなある日のクリスマス。彼はサングラスで素顔を隠し街に出た。そして銀行の預金を全額おろして20ドル札に替えて、なんと街でお金に困っている人たちに配って歩いた。人々に感謝されて、ラリーは嬉しかった。ラリーは、人々の役に立つ仕事をしたいと長距離電話の会社を設立したが、今度は大当たりで、年収もかなり稼ぐ会社になった。裕福になってからも、ラリーは27年間、名前を明かさず20ドル札を配り続けた。およそ700万人の人に、総額約1億8千万円を配った。そして2007年1月、ラリーは癌のため永眠。しかし、その年のクリスマスにもサンタは現れた。彼の遺志を引き継いだ者たちが20ドル札を配ったのだ。
自分が満足したらそれでいいのかもしれない。しかし、自分が大変な時にこそ誰かの為に生きるなら、それ以上のものが返ってくる。
神がこの世にひとり子を与えてくださった。これがクリスマスです。
心のオアシス 2018年11月18日
リバイバリストとして広く知られているイ・ソンボン牧師(1900~1965年)は、次のように感謝したそうです。「私は、自分の元手がゼロの状態で生きてきたので、貧乏になるかと思ったが、かえって金持ちになった。驚くなかれ! 私の資本がどれくらいあるかというと、およそ12億円である。なぜか? 私の身体を作ろうとすれば、ドイツのような科学が発達した国でも、2億円するという。19歳の時に妻に出会ったため、それだけでも、もう4億円である。さらに、愛する娘が4人いるため、すでに12億円の財産がある。私は家に帰るたびに、自分を12億円所有している富豪だと考え、感謝している。もし神さまが私を呼ばれて死んだとしても、損することなど何もない。なぜなら、神さまが下さったこの高価な身体をお返しするだけだからだ。私はこのような人生観をもって生きているので、私の人生はいつも平安で感謝なのである」
「どんな時でも人は笑顔になれる」渡辺和子著の中から、もう一つ・・・
修道服についている大きなポケットを私は「神さまのポケット」と呼んでいます。挨拶や笑顔を、たとえ返してもらえなくても、傷ついたり腹を立てたりするのではなく、自分から挨拶や微笑みをするたびに、神さまへお渡しできるものがポケットに貯まっていくと考えるのです。神さまへお渡しできるものをポケットに貯めておいて、一番いい時に一番いい人に使ってくださるようにと、神さまと約束するのです。私も年齢的にあちこちに出かけていける機会が少なくなっていますが、そんな時にも「今、さみしい思いをしていらっしゃる、おじいちゃま、おばあちゃまがいらしたら、神さま、私の代わりにその方を慰めてください。誰かよこして、そして言葉をかけてください」とお願いするのです。そのためにも、「神さまのポケット」にたくさん貯めておかなければいけません。嫌な方とすれ違っても笑顔を見せる。その笑顔は、見た目には相手の方に対してでありながら「それも神さまに差し上げます」という思いで実行するのです。すると不思議なことに、ちっとも損した気がしなくなります。
つまらない日々も“神”を絡めると得した気分になります!
心のオアシス 2018年11月11日
先日、ある方からメールを受け取りました。この方は、10年ほど前、左顔面痙攣のため脳血管神経減圧手術を受けられ、1回目の手術は失敗。毎日40錠以上の薬を飲みながら戦っておられました。2度目の術後に痙攣は治まったものの、メンタルが壊れ始め、手足が痺れたり、頭痛などの後遺症で悩まされる日々でした。それから数年後、私たちの教会へ導かれ、神さまを信じて受洗されました。それからも季節の変わり目や気圧の変化で身体中の激痛に悩まされてきました。そんな方からのメールに、私自身が励まされました。
「病院に入院しました。先週から酷い頭痛で悩まされMRI検査をしましたが、『血管が詰まったのではなく後遺症の症状なので気を長くして仲良く付き合ってください』と医師から言われました。今更のことではないのですが、なかなか熱も下がらなくて痛みの強さで吐いたりしています。この2,3日前から左の手足の痺れが、今までよりもずっと強く原因もわからなかったのですが、結局は術後の後遺症とのことでした。今は心身共に凄く辛いのですが、考えてみれば自分一人で何も出来なかった時に、いつも助けてくれる方々が傍に居てくれました。主に感謝です! 感謝しきれない神さまの偉大な愛を感じています! 最近はよく泣いていますが、たぶん半分くらいは感謝の涙だと思います。残りの半分も少し時間がかかるかもしれないですが、たかが100年の地上での人生のことであるなら、またつまずくことがあったとしても、天の父なる神さまに信頼して愛して、前向きな姿勢で頑張っていきたいと願っています。いつもありがとうございます。先生のメッセージを聴いて、まだ一歩ですが前に進むことができました。お祈りに心の底から感謝しています。私の小さなうめき声まで、すべてわかってくださるイエスさまに、今日という日を感謝します。」
私はこの方のために祈る時に、「主よ、いつまでなのですか? 早く癒してあげてください!」と文句を言っています。しかし、現状は変わっていなくても感謝しながら歩んでおられる姿に、大変励まされています。