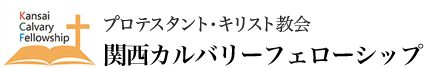各キリスト教会はそれぞれの特徴や強調する部分は違うが、聖書を土台としているなら、キリストの体のどこかの肢体を支えているということになる。パウロ風に表現するならば、目が手に向かって「あなたは必要ない」とは言えないし、頭が足に向かって「あなたは必要ない」とも言えないように、個性の違う相手を批判することは愚かなことである。すべての教会を集めるとキリストの体になるということであろう。
関西カルバリーフェローシップの礼拝の特徴は、教会初心者にとって居心地の良い環境を作るよう努力することである。それは第一コリント9章を要約すると「ユダヤ人を得るためにユダヤ人のようになり、未信者には未信者のようになり、弱い人には弱い者となった。なんとかして幾人かを救うためである。福音のために、わたしはどんな事でもする。私も共に福音にあずかるためである」とあるが、聖書のメッセージは語りつつも初心者の立場に立って違和感を与えないようにする。その工夫については以前にも書いたことがあるので割愛するが、その努力の甲斐あってか、ある方から「初心者を連れて行きやすい教会」と評価してくださった。あるメンバーからは「もう開拓を始めて10年以上も経過し、ある程度の人数も加えられてきたのに、まだ“開拓”と言うのですか?」と問われたことがある。私の答えは「はい」である。“初心者を得るために初心者に配慮する”というのは何年経過しても人数が増えても同じであって、それは開拓当時の心構えをいつまでも持っていたいということの表れである。牧師が変われば、また違う個性の教会になっていくであろう。それも受け留めていく必要がある。
先日、琵琶湖で洗礼式を行なった。実は浸礼(全身を水に沈める)は、礼拝後会衆を解散した後で行なわれることが多いが、滴礼(頭に水をつける)は礼拝の中で短時間に行えるので新来会者もそこに立ち合うことができ洗礼式を見る良い機会にもなる。私たちの教会では滴礼と潅水礼(頭に水を注ぐ)をミックスして行なっている。先日は川か湖での受洗を希望する方がいたので琵琶湖まで行った。「福音のためなら何でもする。」