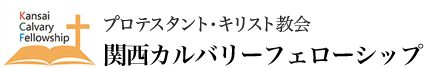8月末にキリシタンの足跡を辿るべく友人牧師と共に長崎の旅をした。今のカトリック教会は、そんなに伝道熱心とは思えないが、16世紀のヨーロッパのカトリック宣教活動には目を見張るものがある。まず飛行機などない時代に、木製の帆船で何ヶ月もかけて日本まで来ることはそれだけでも命懸けであった。この時期に日本へ伝えられたキリスト教は、秀吉から家康の時代にかけて繁栄から激しい弾圧と約250年間にわたる潜伏、そして奇跡と復活という世界でも類を見ない歴史をたどっている。当時の残酷な拷問や処刑方法などは目を覆いたくなるような内容であった。懸賞金のかかった密告が横行する中で、信仰を捨てず生き延びようとするキリシタンたちは二つの道を進んで行く。その一つは「潜伏キリシタン」である。彼らは表向きには寺の檀家や神社の氏子になりつつ、自分たちの秘密組織で信仰を続けていた。そしてキリスト教解禁後に「実はわたしはキリシタンでした」と言ってカトリックへ復帰していった。きちんとした指導者の下へ戻った彼らの信仰は、正しく軌道修正されていったが、もう一つの道、すなわち解禁後も教会へは戻らず自分たちの居心地が良いと感じる道を選んだ人たちは、独自の信仰と様々な宗教との融合へと進んでいった。資料館などの記事によると、彼らはもはや別の宗教となってしまった。これを「隠れキリシタン」と呼んでいる。実は今回知ったのだが、この人たちはまだ現存していて、今も「隠れキリシタン」と呼ばれているとのこと。彼らはいくつかの集落を作り、それぞれが独自の融合宗教を形成していった。そして今は、家族単位のみでその文化や教えを継承していっているが時代と共に衰退している。残念なことであるが改めて“教会”に繋がる大切さを学ばせてもらった。
「ユーチューブ礼拝より、やはり実際に会堂で礼拝すると恵まれ方が違う」という話題をよく耳にする。今の時代は便利にはなった。事情で教会に足を運ぶことができない人たちにとっては絶対に活用すべきツールである。しかし実際に足を踏み入れることによる恵みも大きい。今回の長崎の旅がそうであった。「百聞は一見にしかず」