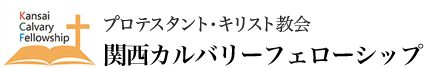日本語の中には、外国語にそのまま訳すことができない言葉がいくつもある。例えば「お裾分け」「こだわり」「わび・さび」「おかげさま」「もどかしい」「ボーっとする」「風物詩」などである。これらに相当する言葉がなく、近い言葉に説明を加えなければ、本当の言葉の意味はなかなか伝わらない。また「いただきます」「ごちそうさま」「おかえり」「お疲れさま」という挨拶の言葉でさえ、海外には似ている言葉はありますが、直訳できる表現はないようです。日本語の背後には、深い意味合いを持つものが多いからです。同じように聖書が書かれた言語(ヘブル語・ギリシャ語)にも、他国の言語に直訳できない言葉がいくつもある。その中の一つに「愛」という言葉がある。古代ギリシアにおける四つの愛の概念は、エロス(eros)=恋愛、フィリア(philia)=友愛、ストルゲー(storge)=家族愛、アガペー(agape)=神の無限なる無償の愛で、それぞれは日本語の中では全て「愛」と訳される。何の愛なのかは説明を加えるか、文脈から読み取らなければ理解することは難しい。
ヨハネによる福音書21章に、イエスさまがペテロに対して「あなたはわたしを愛するか?」と質問され、ペテロは「わたしがあなたを愛していることは、あなたがご存知です」という問答が3回なされたことが書かれているが、この箇所を原文で読んでみると多少意味合いにズレが生じる。最初の2回、イエスさまのペテロに対する質問は「あなたはわたしをアガペー(無条件で愛する)するか?」でした。それに対するペテロの応答は「フィリア(条件付き友愛)していることは、あなたがご存知です」と答えた。そして3度目のイエスさまの質問の時に「わたしをフィリアするか?」と、最初の2回とは違う性質の「愛」という言葉を使われたので、ペテロは心を痛めたと書かれている。彼はイエスさまが捕らえられた時には一目散に逃げ、「イエスなど知らない」と3度も裏切り、もう「無条件で愛する」なんて大言壮語できなかったのです。しかし彼が罪深い者であることを悟った時に神さまに用いられる器になりました。
聖書はその文化的背景や言語を理解して読むと一層深みが増します。