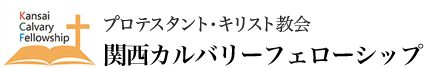「木を見て森を見ず」という格言は、木だけを見ていると、森全体を見ることができないということから、「些細なことにこだわりすぎると、ものごとの本質や全体像を見落とすことがある」という意味で使われていることわざです。聖書は一部の御言葉や譬え話からも大きな励ましを受けることがあるが、その言葉が発せられた状況や歴史的背景などを調べると、もっとリアルに感動することもある。またその言葉の文脈から全体を理解すると深みが増してくる。そしてある時には、今まで理解していた解釈が間違っていたことに気付いたり、わからなったことが理解できるようになることもある。どの視点に立つかがポイントです。
ジョン・マックスウェルの「信仰の法則」という著書に、このようなエピソードがある。大きな街に着いた旅人が、道端に腰を下ろしている老人に「この街の人々はどんな性格ですか」と尋ねた。するとその老人は「ここに来る前に立ち寄った所の人々の性格はどうだったんだい?」と聞き返してきた。旅人が「浅はかな上に、最悪でしたよ」と答えると、老人は「ここの人たちも同じだよ」と言いました。数日後、また別の旅人がその街に来て、その老人に同じ質問をしました。今回もまた、旅人がそこに来る前に訪れた所の人たちはどうだったかと尋ねると、「正直でまじめな上に、心の広い人がたくさんいました」と旅人が答えると、老人は「ここにも良い人がたくさんいますよ」と言いました。
ジョン・マックスウェルは、これを「レンズの原則」と説明しています。つまり、人によって、状況や相手を見る観点が違ってくるというのです。神さまに信頼を置いている人たちが用いるべきレンズは、「イエス・キリスト」です。“神の視点”から人や現実を見ることによって、人を批判して落とし入れるのではなく、尊ぶことができるようになります。自分は罪人で、イエスさまの身代わりの十字架によって救われたにしかすぎない存在であることを知っている人は、人をぞんざいに扱ったりはしません。問題に対して不平不満ではなく、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝する心が与えられるから不思議です。